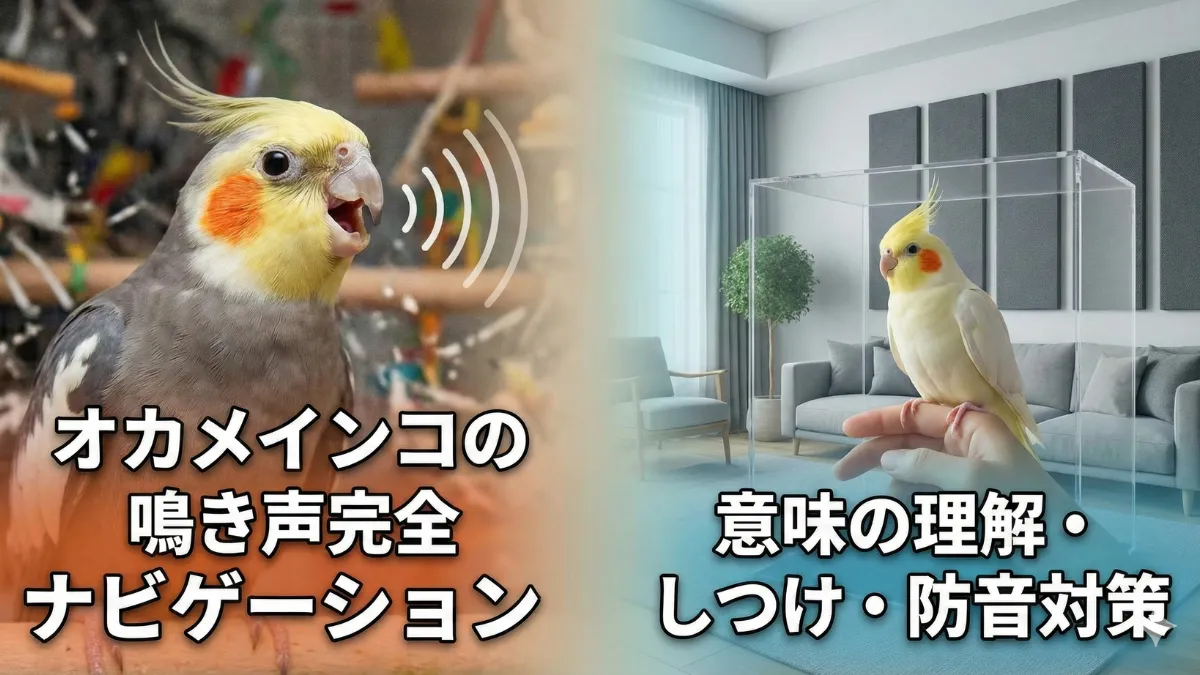オカメインコの鳴き声の種類と意味|8つのパターンを完全解説

オカメインコは非常に表現豊かな鳥で、さまざまな鳴き声を使い分けてコミュニケーションを取ります。愛鳥の気持ちを理解するために、まずは代表的な8つの鳴き声パターンを覚えましょう。
オカメインコの代表的な鳴き声8種類
- 呼び鳴き:飼い主への愛情表現と注目要求
- 地鳴き:日常的な自己表現と安心の証
- 求愛ソング:オスの発情期の特徴的な鳴き声
- 警戒音:危険を察知した時の短く鋭い声
- 威嚇音:不快感や怒りを示す低い声
- 甘え鳴き:リラックスした小さな鳴き声
- 雛鳴き:幼鳥特有の餌をねだる声
- 夜鳴き:夜間の不安や恐怖による鳴き声
これらの鳴き声を理解することで、愛鳥が今何を求めているのか、どんな気持ちなのかを正確に把握できるようになります。それぞれの鳴き声について、詳しく見ていきましょう。
ちなみに、オカメインコは野生では群れで生活する鳥です。そのため、仲間とのコミュニケーションを取るために鳴くことは本能的な行動であり、完全に鳴かなくすることは不可能です。適度な発声は健康な証拠ですので、過度な静けさを求めすぎないようにしましょう。
品種による鳴き声の違い
オカメインコは品種によって性格や体格が異なり、鳴き声にも微妙な違いがあります。
- ノーマル・パール:比較的活発で鳴き声も元気
- ルチノー・ホワイトフェイス:おとなしい個体が多く、鳴き声も控えめな傾向
- パイド・シナモン:個体差が大きく一概には言えない
呼び鳴き|ピュイピュイと飼い主を呼ぶ愛情表現
呼び鳴きは、オカメインコが飼い主に注目してもらいたい時や、寂しさを感じた時に発する鳴き声です。ピュイピュイ、キュイキュイといった高めの声で、連続的に鳴くのが特徴です。
呼び鳴きの心理とは
オカメインコが群れで生活する習性を持つため、一羽飼いの場合は飼い主を家族や仲間と認識します。そのため、飼い主が見えているのに一緒にいられないと、呼び鳴きで注目を引こうとするのです。
野生では仲間とコミュニケーションを取るために鳴くことが自然な行動であるため、適度な呼び鳴きは愛情表現として受け止めてあげましょう。ただし、過度な呼び鳴きは問題行動につながる可能性があるため、適切な対応が必要です。
ピュイと鳴く意味と正しい対応法
「ピュイ」という鳴き声は、オカメインコの呼び鳴きの中でも特に多く聞かれる代表的なパターンです。この一声には、不安、甘え、要求など、さまざまな意味が込められています。
ピュイへの正しい対応の具体例
不安そうに「ピュイ…」と鳴いた時と、要求が強い「ピュイピュイ!」では対応を変えることが大切です。
応答する時(不安の解消)
- セリフ例:「なあに?」「〇〇ちゃん(名前)、ここにいるよ」「大丈夫だよ~」など、短く優しい言葉を選びましょう
- 行動例:別の部屋にいるなら、声だけで返事をします。同じ部屋にいるなら、優しく微笑みかけてあげましょう
距離を置く時(要求の抑制)
- 行動例:目を合わせず、背中を向けます。テレビを見たり、本を読んだり、別のことに集中しているフリをしましょう
- ポイント:完全に静かになった瞬間に、「静かにできてえらいね!」と優しく声をかけます
オスとメスの鳴き声の違い
オスとメスでは鳴き声に明確な違いがあります。この違いは性別判定の重要な手がかりになります。
求愛ソングは、オカメインコが性的に成熟したサインでもあります。通常、生後6ヶ月から1歳ごろから始まり、春から夏にかけての繁殖期に特に活発になります。
オスとメスの見分け方について詳しく知りたい方は、オカメインコのオスメス見分け方完全ガイドをご覧ください。
その他の鳴き声(警戒音・威嚇音・甘え鳴き・雛鳴き・夜鳴き)
警戒音は、オカメインコが何か危険や不安を感じた時に発する短く鋭い鳴き声です。ピッ、ピーッといった高い声で、緊張感が伝わってきます。この鳴き声が聞こえたら、愛鳥が何に警戒しているのかを確認しましょう。
威嚇音は、オカメインコが不快感や怒りを示す時に発する低い声です。ジージー、シャーッといった音で、時には羽を広げたり、くちばしを開いたりする仕草を伴います。この鳴き声が聞こえた時は、愛鳥に無理に触ろうとせず、距離を置いて落ち着かせましょう。
甘え鳴きは、オカメインコがリラックスして甘えている時に発する小さな柔らかい鳴き声です。キュッキュッ、クルクルといった優しい音で、撫でられている時や、飼い主の近くでくつろいでいる時によく聞かれます。
雛鳴きは、幼鳥が餌をねだる時に発する特徴的な鳴き声です。ジャージャー、ジュージューといった連続的な音で、親鳥や飼い主に向かって口を大きく開けながら鳴きます。挿し餌の時期が終わっても、しばらくは雛鳴きが続くことがありますが、徐々に減っていくのが通常です。
夜鳴きは、本来静かにしているべき夜間に鳴く現象です。悪夢を見たり、周囲の音に驚いたり、不安を感じたりすることが原因と考えられます。夜鳴きが頻繁に起こる場合は、ケージカバーをかけて安心感を与える、静かで暗い環境を整える、就寝前のルーティンを確立するなどの対策が効果的です。
夜間のオカメパニックについては、オカメパニック対策ケージガイドで詳しく解説しています。
オカメインコの鳴き声がうるさい!原因別の効果的な対策としつけのコツ

オカメインコの呼び鳴きがうるさくて困っている飼い主さんは少なくありません。しかし、多くの場合、飼い主さん自身が気づかないうちに呼び鳴きを強化してしまっている(鳥からしつけられている)ケースがあります。
実は、「鳥にしつけられていた」という気づき
多くの飼い主が気づかないうちに陥る失敗パターンがあります。
悪循環のパターン:
オカメインコが鳴く → 飼い主が出す → 鳴けば出してもらえると学習 → もっと鳴く
ある飼い主さんの証言:
「ルナがあまりにうるさく鳴くのでその都度出すようにしていたら、呼び鳴きがどんどんエスカレートしていき、遠くから私の姿が見えただけでも呼び鳴きするようになっていきました。ある日ふと、『これって私がルナにしつけられているのでは…?』と気づいたものの、時すでに遅し。」
呼び鳴きがうるさい原因を理解し、科学的根拠に基づいた対策を実践することで、お互いにストレスの少ない生活が実現できます。以下では、原因別の具体的な対策方法をご紹介します。
呼び鳴きの主な原因
- 寂しさや分離不安(飼い主への強い愛着)
- 退屈や刺激不足(ケージ内での時間が長い)
- 要求行動の学習(鳴けば出してもらえると覚えた)
- 発情期の影響(ホルモンバランスの変化)
- 環境の変化やストレス(引っ越し、模様替えなど)
無視と褒めるのバランス|効果的なしつけの基本

呼び鳴きのしつけで最も効果的な方法は、「無視」と「褒める」を適切に使い分けることです。ただし、この方法には注意すべき重要なポイントがあります。
消去バーストという最大の試練
しつけを始めると、必ず訪れる「消去バースト」という現象を理解しておくことが重要です。
消去バーストとは?
自動販売機の例で理解しましょう:お金を入れてもジュースが出ない時、人はボタンを何度も、より強く押します。これが「消去バースト」です。
呼び鳴きで考えると:
-
呼び鳴きを無視し始めたら、鳥は一時的にもっと大きな声で鳴き続ける(バースト) -
ここで耐えきれずに構ってしまうと、鳥は「極端に激しく鳴けば、飼い主は必ず構ってくれる」と学習 -
結果として、問題行動がさらに悪化する
対処法:
消去バーストの時期を乗り越えることが成功の鍵です。一時的に鳴き声が激しくなっても、決して応じないことが重要です。この試練を乗り越えれば、鳥は「鳴いても無駄だ」と学習し、呼び鳴きが減っていきます。
正しい無視と褒めるのタイミング
鳴いている時:
- 完全に無視する(目を合わせない、声をかけない、近づかない)
- 「うるさい」「静かにして」などの声かけもNG(反応したことになる)
- ケージを叩くなどの罰もNG(恐怖心を与えるだけ)
静かになった時:
- すぐに褒める(「静かにできてえらいね!」「いい子だね!」)
- 優しく声をかける、微笑みかける
- おやつをあげる(ご褒美の強化)
- ケージから出してあげる(静かにしていたら出してもらえると学習)
呼び鳴き対策の詳細については、インコの呼び鳴き対策完全ガイドもご覧ください。
定時放鳥スケジュール|予測可能性が呼び鳴きを減らす
呼び鳴きが激しい原因の一つに、「いつ出してもらえるか分からない不安」があります。毎日決まった時間に放鳥することで、オカメインコは「いつ出してもらえるか」を予測できるようになり、それ以外の時間は静かに待つことを学習します。
理想的な放鳥スケジュール
- 毎日最低1時間程度の放鳥が理想的
- 朝と夕方の2回に分けるとより効果的
- 飼い主の生活リズムに合わせた定時放鳥が望ましい
- 放鳥時間の前に鳴いても出さない(時間を守る)
重要なのは放鳥の時間帯や長さを一定にすることです。不規則な放鳥スケジュールだと、いつ出してもらえるか予測できずに呼び鳴きが増えてしまいます。
成功体験談:ケージ配置変更と定時放鳥
成功事例1:ケージ配置変更で改善
「ケージの位置をパソコンデスクの上に移動した結果、呼び鳴きが大幅に改善しました。孤独感が原因だったため、飼い主の存在を感じられる場所への配置が効果的でした。」
成功事例2:消音強化法の実践
「最初は無視するのが辛かったですが、根気強く続けました。2週間ほどで効果が出始め、今では短く鳴いて反応がないとすぐに諦めるようになりました。ポイントは、静かになったらすぐに褒めること。このメリハリが大切だと思います。」(20代男性の体験談)
成功事例3:リビングへの移動
「ケージを寝室から家族が集まるリビングに移動しただけで、呼び鳴きが半分以下に減りました。」(40代女性)
しつけの失敗例と限界を理解する

しつけは万能ではありません。現実的な期待値を持つことが、飼い主さんの精神衛生上も重要です。
しつけの失敗例と限界の現実
成功事例:
-
「呼び鳴きをしたら前扉を閉める」というルールで学習させた個体 -
「うるさいよー」「しーっ」という決まった言葉で静かにする個体もいる
失敗例の現実:
-
「半年経っても改善の兆しが見えない」ケース -
「一日中ホイヨホイヨと鳴き続ける」個体 -
「さし餌雛から大事に育てても効果が見られない」場合もある
しつけの限界:
個体差が非常に大きく、どんなに努力しても改善しない個体も存在します。「しつけで完全にコントロールできる」という期待は危険です。
重要なのは、完璧を目指すのではなく、「お互いにストレスが少ない妥協点を見つける」ことです。
家族全員の協力が絶対必須|一人でも例外を作ると失敗する

オカメインコのしつけで最も見落とされがちなのが、家族全員の協力体制です。一人でも例外を作ると、すべての努力が水の泡になってしまいます。
成功例(一人暮らし)
「当時の私は一人暮らしでしたから、『ルナがかわいそう』などと口を挟んで、ルナと私のトレーニングを邪魔するような家族が同居していなかったことも幸いして、何とかこのしつけを続けてこれたのでした。
しかし、私もルナに負けないくらいしつこい性格なので(笑)決めた1点を根気よく、諦めずに続けました。」
失敗例(同居家族あり)
「私は無視を徹底していましたが、同居している母が『かわいそう』と言ってつい構ってしまい、3ヶ月の努力が無駄になりました。家族全員の協力がないと絶対に成功しません。」(30代女性)
家族全員が同じルールを守ることが絶対条件です。一人でも「かわいそう」と言って例外を作ると、オカメインコは「誰かが必ず応じてくれる」と学習してしまいます。
ケージ内の時間を充実させる環境作り|お家にあるもので簡単フォージング

呼び鳴きのしつけと同時に、オカメインコが自分で楽しめる環境作りも重要です。ケージ内での時間が充実していれば、退屈から来る呼び鳴きは自然と減っていきます。
「防音グッズを買う前に、まずは無料でできることから試したい」という方におすすめなのが、お家にあるもので作る簡単なフォージングです。
お家にあるもので作る簡単フォージング
実践例:
「オカメインコの呼び鳴きのしつけと同時進行で、ルナが一人遊びできるようなインコ用のおもちゃをケージの中に入れました。また、時々大好きな粟穂を入れたり、好物を仕込んだフォージングトイを入れたりして、少しでもルナの気がまぎれるように配慮しました。」
- 紙コップ:底に穴を開けて粟穂を差し込む。インコが引っ張り出して食べる楽しみを提供
- 麻紐:好物のペレットを麻紐に通して吊るす。採餌行動を促す
- 小さな紙袋:中におやつを入れて閉じる。破って探す楽しみ
- キッチンペーパーの芯:中におやつを入れて両端を折り込む。破壊系おもちゃとして最適
効果:
採餌行動(フォージング)を促すおもちゃは、野生の本能を満たすことができるので特に効果的です。ケージ内での時間が充実すれば、呼び鳴きも自然と減っていくでしょう。
フォージングトイの選び方や手作り方法については、インコのおもちゃは家にあるもので手作り!簡単フォージングのすすめで詳しく解説しています。0円でできる工夫がたくさん紹介されているので、まずはこちらを試してから防音グッズの購入を検討するのも良いでしょう。
マンション・アパートで飼うなら「防音対策は義務」|物理的にシャットアウトする方法

「しつけで静かにさせよう」と考える前に、まず理解していただきたいことがあります。オカメインコに「鳴くな」と教えるのは、鳥の本能を否定することであり、ストレスを与える行為です。完全に鳴かなくすることは不可能ですし、健康にも良くありません。
だからこそ重要なのが、物理的に音をシャットアウトする防音環境の構築です。「鳴いても近隣に聞こえない」状態を作ることで、あなたも愛鳥も、そして近隣の方もストレスなく暮らせます。
オカメインコの騒音レベルは90dB|地下鉄の車内と同等
「オカメインコの鳴き声ってそんなにうるさいの?」と思っている方に、まず知っていただきたい事実があります。オカメインコの呼び鳴きは、騒音計で測定すると約90dB(デシベル)に達します。これは地下鉄の車内や、工場の機械音に匹敵する騒音レベルです。
騒音レベルの目安
重要:防音対策は「マナー」ではなく「義務」
マンションやアパートでオカメインコを飼うなら、防音対策は任意のマナーではなく、近隣との共生のための義務です。「少しぐらい大丈夫だろう」という甘い考えは、後々の深刻なトラブルにつながります。
特に木造アパートや壁が薄い物件では、90dBの呼び鳴きは隣室にほぼそのまま聞こえていると考えてください。在宅ワークが増えた現代、日中の騒音に対する感覚も以前より敏感になっています。
カーテン vs アクリルケース|防音効果の数値比較
「防音カーテンを買えば大丈夫」と思っている方も多いのですが、実際の防音効果は期待するほどではありません。以下の表で、各防音対策の実測値を比較してみましょう。
なぜアクリルケースが最強なのか?
高音域の音(オカメインコの鳴き声)は、隙間から漏れやすいという物理的な特性があります。カーテンやカバーは布製で隙間が多いため、高い音を遮断できません。
一方、アクリルケースは密閉性が高く、音を物理的に遮断します。特に5mm以上の厚手のアクリル板を使用したケースなら、-30dBの防音効果が期待できます。これは90dBの呼び鳴きを60dB(普通の会話レベル)まで下げられることを意味します。
防音グッズの詳しい比較については、インコの防音グッズランキングで実測データと共に解説しています。
おすすめの防音グッズ
本格的な防音対策には、以下のグッズを組み合わせることをおすすめします。
②吸音材
壁や天井に貼り付ける吸音パネル。アクリルケースと併用することで、さらに防音効果が高まります。特に窓際や隣室との壁に設置すると効果的です。賃貸でも使える両面テープタイプがおすすめ。
③窓用防音ボード
最も音が漏れやすいのは「窓」です。カーテンだけでは不十分なので、窓にはめ込むタイプの防音ボードを使用しましょう。賃貸でも使えるワンタッチタイプが便利です。
注意:自作・100均グッズはおすすめしません
ダンボールやプラスチックケースでの自作は、火災リスクがあり、防音効果も限定的です。「安く済ませたい」という気持ちは分かりますが、結局買い直すことになり、かえって高くつきます。最初から信頼できる製品を選びましょう。
年齢・時間帯別の鳴き声の特徴と対策

オカメインコの鳴き声は、年齢や時間帯によって特徴が異なります。それぞれのライフステージや時間帯に応じた対策を知ることで、より効果的に騒音問題に対処できます。
雛(生後0〜6ヶ月)の特徴
雛の時期は、餌をねだる「ピーピー」という鳴き声が中心です。騒音レベルは70dB程度で、成鳥の呼び鳴きに比べると控えめです。
雛期の対策
- 適切な温度管理(28〜30℃)で安心感を与える
- 定期的な挿し餌で空腹を防ぐ
- この時期から「無視と褒める」の基本を教え始める
オカメインコの雛の育て方については、オカメインコ雛の育て方完全ガイドで詳しく解説しています。
若鳥(生後6ヶ月〜2歳)の特徴
最も活発で、呼び鳴きが激しくなる時期です。特にオスは生後8ヶ月頃から求愛ソングを歌い始め、騒音レベルは80〜90dBに達します。しつけの効果が最も出やすい時期でもあります。
若鳥期の対策
- 十分な運動時間(1日2時間以上の放鳥)
- 無視と褒めるを徹底して、呼び鳴きの習慣をつけない
- 発情抑制(日照時間を12時間以内に調整)
- アクリルケースなどの防音対策を本格導入
成鳥(2歳〜15歳)の特徴
個体差が大きくなる時期です。若鳥期にしつけが成功していれば、呼び鳴きは比較的落ち着きます。ただし、飼い主への愛着が深まることで、分離不安による呼び鳴きが激しくなることもあります。
成鳥期の対策
- 規則正しい生活リズムの維持
- 過度な甘やかしを避ける(適度な距離感)
- 新しい呼び鳴きの習慣がつかないよう、引き続き無視を徹底
シニア(15歳以上)の特徴
体力が落ちるため、呼び鳴きの頻度は減少する傾向にあります。ただし、視力・聴力の低下による不安から、急に鳴き声が増えることもあります。
シニア期の対策
- 静かな環境を提供(音や光の刺激を減らす)
- ケージの配置を変えない(慣れた環境が安心)
- 体調の変化に注意し、異常があればすぐに受診
オカメインコの寿命と年齢別の健康管理については、オカメインコの平均寿命ガイドをご覧ください。
時間帯別の鳴き声対策
オカメインコは、時間帯によって鳴き方が変わります。特に問題になりやすい時間帯の対策をまとめました。
FAQ|オカメインコの鳴き声に関するよくある質問

オカメインコの鳴き声ガイド【総括】

オカメインコの鳴き声は、愛情表現であり、健康な証拠であり、生きる喜びの表れです。しかし、その鳴き声が90dBの騒音レベルに達することを忘れてはいけません。マンションやアパートで飼うなら、防音対策はマナーではなく義務です。
この記事では、オカメインコの8種類の鳴き声の意味、「ピュイ」への具体的な対応法、無視と褒めるバランスの取り方、消去バーストの乗り越え方、家族全員の協力の重要性、そして物理的な防音対策まで、網羅的に解説してきました。
重要なのは、「鳴くな」と教えるのではなく、「鳴いても近隣に聞こえない環境」を作ることです。アクリルケースによる物理的な遮断(-30dB)と、無視と褒めるを徹底したしつけ、この二つの両輪で、あなたも愛鳥も、そして近隣の方も快適に暮らせる環境が実現します。
しつけには数ヶ月から1年以上かかることもありますが、諦めずに一貫した対応を続けてください。途中で諦めてしまうと、それまでの努力が水の泡になります。消去バーストを乗り越えた先に、静かで穏やかな日常が待っています。
オカメインコとの暮らしは、時に大変なこともありますが、その愛らしさと賢さは、あなたの人生を豊かにしてくれるはずです。正しい知識と愛情深いケアによって、愛鳥との快適な共同生活を実現してください。
📗 インコの防音対策をもっと詳しく知りたい方へ
本記事ではオカメインコの鳴き声と対策をご紹介しましたが、インコ全般の防音対策に関する情報はまだまだあります。セキセイインコ、オカメインコ、コザクラインコなど、種類別の騒音レベル比較、賃貸物件での具体的な防音施工事例、近隣トラブル回避の実践テクニックなど、総合的な防音ガイドをご用意しています。